このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。
「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、
「もちろん!」と嬉しいお言葉。
ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。
2013/05/07
Vol.85 般若心経展が終わる

この手の展示としては長い9日間が終わった。
多くの人が顔を見せてくれた。
仲間たちの絵が売れたことも嬉しかった。
多くの人々の絆に感謝、感謝である。
いろいろ忘れがたい出会いや出来事があった。
初日の夜には、北パキスタンから来られた
バダル・アリー・ハーン氏率いるカウワーリー五重奏団の
イスラーム神秘主義集団歌謡カウワーリーと日本の尺八やベースギター、
ドラムスのコラボ演奏会が、フェースの般若心経壁画を背景に
開かれた。
異文化圏の器楽や祈りの歌唱、それにフェースのアートが出会い、
融合し、不思議なエネルギー空間が生まれた。
忘れがたい夜の時間を持つことができた。

また今回の展示会で、としきさんは
似顔絵画家の一歩を踏み出した。
土蔵の中の小さなテーブルに初めての人と向かい合い、
さらさらと似顔絵を仕上げていったのだ。
あまりにも、すんなり描いていくので、
どんどん描いてもらったら、4人目でとうとう怒りだしたけれど、
独特の構図、タッチで、としきさんテーストの立派な肖像画だった。
ワタシなんかは、鎌倉の参道で似顔絵かきでもやったらどうだろうと、
つい本気で思ってしまったほどだ。

ひのさんのボールペンで描かれた細密な点描や線描の作品には、
多くの人が目を止めてくれた。
かなりの値段がつけられた「草の世界」という作品には、
二人のコレクターから購入希望があったほどだ。
ふだん、フェースの仲間たちと絵を描いているだけでは、
なかなか得られない刺激や可能性を得ることができた。
今回の展示会の体験は、これからのフェースの大切な礎になるだろう。
200人を超える人たちと共同し、様々な結びつきを作ってきた
「ワンダーな般若心経」プロジェクトはこれで完結するのではなく、
今も途上にある気がする。
ワタシは大きな大河を海に向かって下るような気持で、
こんごも、このプロジェクトを考えていきたいと思っている。
最後に、こうしたわがままな展示会をギャラリー企画として取り上げてくださった
佐野さんに深く感謝する。
生きていくこととアートすることが交差する場作りに
これからも励みたいとあらためて思う。
ありがとうございました。

△ページトップへ戻る
2013/05/03
Vol.84 人と人を結びつける文字

この数年、仲間たちが描きつづけたアート文字は、
その時々の心の断片のように、いろいろな風景をボクに思い起こさせた。
ギャラリーの壁の中心に展示している「三」という文字は、
今回の展示を進めるうえで、ボクには大切なカギとなる文字だ。
この文字は、三つの直線で描かれているが、
等間隔三つの直線にするために、
お母さんが文字をかかない仲間の手を取って描いたものだ。
その光景を目にした時、
ボクは、般若心経の文字を
仲間たちの描線や色彩と融合させ、
生命讃歌の大きなタペストリーにしようと考えた自分の傲慢さを
思わずにはいられなかった。
一方的な自分の想いを仲間に押し付けようとしているんじゃないか?
その自問に答えることが、
このプロジェクトのボクの大切な課題になった。
そして、お母さんと仲間が「三」という文字を描く光景は、
一つの表現の在り方をボクに教えてくれた。
それまでは、一人一文字でかいていこうと思っていたのだが、
文字がかける、かけないという地平を超えて、
一つの文字もみんなで描いていけばいいのだ、
それぞれが参加できる形で
みんなで共同して般若心経を作っていけばいいのだ、
という考えに辿り着いたのだ。
そういう体験を仲間たちやボクだけでなく、
フェースを支えてくれている多くの人たちと共有することが
今回のプロジェクトの大きな意義なのだと気付いた。
「羯」という文字を描く時は、
「羊」とか「日」とかに分割して、一つの文字に組み立てたりした。
そして、フェースの般若心経では
正確な文字であるとことやきれいな文字であることは、
大して重要なことではなくなった。
かけない文字は、みんなで工夫してそれらしく作り上げる。
バラバラにした文字に目玉やしっぽをつけて、
それを積み木のように組み立て、楽しんでみる。
読めなくても、「まあいいんじゃない」。
そんな風にしてなんでもありの自由感とか共遊感が生まれていった。
やがて、文字作りはもっともっとオープンになり、
出会う人ごとに声をかけ、短時間でさっとかいてもらうようになった。
いろいろな文字が生まれた。

正直、ボクは舌を巻いた。
般若心経は、
経文の意味を知らないのはもちろんのこと、
文字ひとつ満足にかけないボクたちを、
より自由に表現自体を楽しむ世界へと解放させてくれたのだ。
それまで出会うことのなかった人たちも巻き込みながら、
大きな渦のような流れを今も巻き起こしている。
3.5m×6mの折れ曲がったギャラリーの壁には、
崩れかけたパズルや人体解剖図のような文字、
立派な楷書の文字・・・、
それらがギャラリーの壁面で、
同じように存在し、宙を漂っている。
会場に来た人は自由に文字をかき、壁に貼り付けることができる。
ぜひ、あなたも、
アナタの文字をワンダーな般若心経の世界に投じてほしい。

△ページトップへ戻る
2013/04/30
Vol.83 人やモノがいききする般若心経

フェースofワンダーの「ワンダーな般若心経展」がはじまった。
なかなか面白いと好評(かな?)。
展示準備の三日間も楽しかった。
いろいろな人が時間を見つけては、入れ替わり立ち代わり、
アート文字を蔵まえギャラリーの壁に貼り続けてくれた。
展示している間も、仕事帰りの大工さんや町内会のおじさん、
ぶらぶら歩きのおじいちゃん、犬を連れたおばさん・・・、
通りすがりに、開け放したギャラリーに入ってきては、
壁を覆い尽くす色彩と文字の前に立ち、口をあんぐり。
みんな、何を言っていいのかわからず唸っていた(笑)。
仲間たちの描いた抽象模様の背景の中には、
今年の岡本太郎現代芸術賞に入選した鷲尾圭介さんの
巨大なラッコの絵も混じっていて、
それはさすがに具象で分かりやすく、ホッとした感じで
「あれはラッコだよな。うん、うん、可愛いよなあ・・・」
「線がぐにょぐにょ曲がりくねってるから、目がくらくらする。」
「何だかわからないけれど、体が熱くなるわ」
いろいろな感想が飛び交った。
「展示期間中にもう一回来て、般若心経の文字を描いて、
この絵に貼ってよ」
そんな依頼をすると、かならずみんな一度は退くが、
接待上手のオーナーの佐野さんが、お茶やせんべいを差し出しながら、
「読めなくてもいいのよ。色を少し塗るだけだっていいんだから」
と、声をかける。
出会ったばかりの人と茶を飲みながら、
「障がいのある、なしじゃなく、うまいとか下手とか関係なく、
みんなの色や文字がここに集って流れている、
そんな作品にしたいんですよ。」と話すと、
なんとなく、みんなしっかり聞いてくれるのが嬉しい。
たまたま、ギャラリーの二階では「写経教室」が開かれていて、
仲間たちの文字を見せると、
「これはどう読むんだろう?」とか
「こんなストレートに文字はぜったいかけない」とかいろいろ
話が盛り上がり、
その日、彼女たちが書いたばかりの写経も貼ってもらうことになった。
今回の「ワンダー般若心経」には、
いろいろな人、ことば、文字がいき交って、
いまも膨張を続けている。
ぜひ、あなたも文字を描きに来てくださいね。

△ページトップへ戻る
2013/04/23
Vol.82 お待ちしています

拝啓
お元気ですか?
ずっと走り続けているアナタの額の汗が目に浮かぶようです。
いよいよゴールデンウィークですね。
4月29日から5月7日まで、藤沢にある蔵まえギャラリーで
フェースofワンダーの仲間たちと
「ワンダーな般若心経」展なるものを開催します。
構想から5年、
まだ途上にありますが、
縁あって、世に問う機会を得ました。
形にもならない私たちの作品ですが、
般若心経という器に盛ると、どのように姿を変えるのか?
ご高覧いただければ有難く存じます。
一年で一番、光や風が輝く季節。
緑陰の中にいて、
時々、アナタのことを想います。
街中の騒音の中にいて、
アナタの声を聴きたいと思ったりします。
どうか、がんばりすぎないでください。
忙しい日々の一日、
湘南まで足を延ばして、
フェースの仲間たちの作品に会いに来てください。
般若心経の渦巻く色彩や形の中に
アナタが求めていた何かが見つかれば、
とてもうれしく思います。
心より、お待ちしています。 敬具
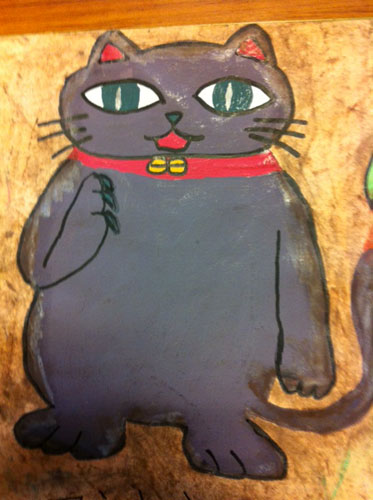
△ページトップへ戻る
2013/04/23
Vol.81 それぞれが自由でいたい

いま、頭を悩ましていることがある。
4月29日から始まる「ワンダーな般若心経展」に
仲間の作品をどう展示するのがいいのか、
アイデアが浮かんでこないのだ。
今回のメインの展示は、
仲間たちや協力者と一緒に描いたアート文字。
3.5m×6mの壁に
仲間たちの色彩や模様を貼り付け、
その上にピンでとめていく。
多分、湧き上がる色彩の巨大な雲や
雪崩れ落ちる線に、
仲間たちの文字は自在のおしゃべりを始めるだろうから、
それはそんなに心配していない。
(期間中、見に来てくれた人にも、
アート文字を描いてもらい、貼っていくから、
般若心経は、きっと巨大な渦巻きのようになるだろう・・・)
問題は個人作品をどう活かすかなのだ。
大きさもテーマも違うし、額装もしない。
ボクとしては、
仲間の作品に一人ひとりのおしゃべりやジャンピングダンスを
見ることが多いので、その軽やかな自由感、
うまい・下手を超えた、生きてることの楽しさが出ないかと
考えているのだ。
よくある作品展のように、一点々にタイトルと作家名をつけて、
間隔をあけて、きれいに展示する。
あれはもう嫌なのだ。
作品が虫の標本箱のように見える。
等間隔に並べられ、多くの人の視線にさらされる
孤独な悲しさがある。
もっと、自由に、
それぞれが仲間たちの一人となり、
一人ひとりのおしゃべりやジャンプが
輝いているような、
そんな展示ができないだろうか?

△ページトップへ戻る

