このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。
「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、
「もちろん!」と嬉しいお言葉。
ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。
2014/12/12
Vol.245 Vividの道を往く賢治の背
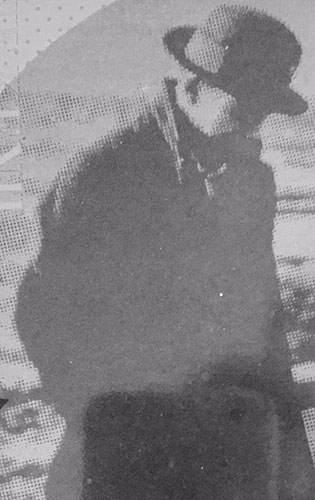
中原中也の「宮沢賢治の詩」と題された文章に出会った。
わずか12行。
「・・・彼は幸福に書き付けました、とにかく印象の生滅するままに自分の命が経験したことのその何のぶぶんをだってこぼしてはならないとばかり。それには概念を出来るだけ遠ざけて、なるべく生の印象、新鮮な現識を、それが頭に浮かぶままを、・・・つまり書いている時その時の命の流れをも、むげに退けてはならないのでした。
彼は想起される印象を、刻々新しい概念に、翻訳しつつあったのです。彼にとって印象というものは、或いは現識というものは、勘考さるべきものでもない、そんなことをしてはいられない程、現識は現識のままで、惚れ惚れとさせるべきものであったのです。
それで彼は、その現識を出来るだけ直接に表白出来さえすればよかったのです・・・」
読みながら、仲間たちが絵を描いている光景が浮かんできた。
幾つもの仲間の絵が、それに重なるように現れてきた。
これって、中也による賢治風Vividアートの解説書(レシピ)みたいじゃないか。
そうかオレたちは、賢治の後を追っかけてきたんだ。
100年も前の賢治の猫背が、チラリと100年後の冬の陽射しが射す部屋の向こうに見えたような気がした。
それから、積み上げた本の山から「春と修羅」第一集を探し出し、序を開いた。
「・・・これらは二十二か月の/過去とかんずる方角から/紙と鉱質インクをつらね/(すべてわたくしと明滅し/みんなが同時感ずるもの)/ここまでたもちつづけられた/かげとひかりのひとくさりずつ/そのとおりの心象スケッチです・・・」
そのように素描の方法論が平明に書かれている。
その後には優しい先生のような説明の言葉が続いている。
「・・・これらについて人や銀河や修羅や海胆(うに)は/宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら/それぞれ新鮮な本体論も考えましょうが/それらも畢竟心の一つの風物です/ただたしかに記録されたこれらのけしきは/記録されたそのとおりのこのけしきで/それが虚無ならば虚無自身がこのとおりで/ある程度まではみんなに共通します/(すべてがわたくしの中のみんなであるように/みんなのおのおののなかのすべてですから)・・・」
そういうことだったんだとワタシは、辻堂のネコの師匠や青い石をもつカエルや人である仲間たちを思い浮かべる。
この序が書かれた1924年から90年後のワタシは、もうなんの不安やてらいもなく賢治の心象スケッチをめくることができる。
ワタシたちはワタシたちの心象スケッチを記録していこう。
ワタシたちはたしかに、
風景やみんなといっしょに/せわしくせわしく明滅しながら/いかにもたしかにともりつづける/因果交流電燈の/ひとつの青い照明です/・・・ですから、
そのように明滅しながら、前を往く賢治の背を見ながらまっすぐ歩いていけばいいんだと、
ワタシは励まされる。

2014/12/09
Vol.244 白磁に陽があたる

冷え込んだ朝、一枚の写メールが届いた。
窓際に置かれた白磁の器と紅葉した小枝がひとさし。
画面を対角線によぎるように並べられた白い器は静かで美しい。
沙羅樹(ナツツバキ)だという紅葉の先には、紡錘形をしたやわらかな冬芽が見える。
送り主のGさんは有田で陶磁器を作っている作家なので、写真の器は彼の作品なのだろう。
朝の澄んだ光が白磁に斜めの影模様をつけている。
もしかしたら、表面には浅くなめらかな溝がつけられているのかもしれない。
一個一個の器の形は、ボクには不安定に見える。
これが花器なのか湯呑みなのか、ボクは知らないが、ここに茶を入れたとしたらボクは飲む前に、器と緊張したやりとりをしなければいけないかもしれない。
例えば、湯によって暖まっていく器が心臓のようにゆっくり鼓動を打ち始めるのを聴くかもしれない。
器がまとった灰色の淡い影を一枚いちまい剥いでみたくなるかもしれない。
指先で縁をピーンとはじいて、その音の行方を探すかもしれない。
あるいは、お茶ではなくて、絵の具を落として白磁の肌に広がる色を楽しむかもしれない。
そんな風にモノと対峙する時間はボクの生活の中では極めて少ないので、お茶を飲む時間を大切にするようになるかもしれない。
そんな風にして、器は日常の時間ともう一つの時間をつなぐ回路になるかもしれない。
そう考えると、ボクはホッとする。
Gさんがどのような意図のもとに、これらの器を作られているのかボクは知らないけれど、ボクには、これらはGさんの心象を映し出した繊細で孤独なオブジェではなく生活雑器として存在したがっているように見えてきたからだ。
生活の中にこれらが置かれること、これらの存在する場所が生活時間の中にあること。
それは、いまボクが仲間たちの活動から教えられていることと同質のものを教えてくれるかもしれない。
そう思って、あらためて器たちを見ると不安定な形の面白さに気づく。
ちょっとよろけながら、
それから斜めに傾ぎながら、
腰を折り、ため息をつき・・・
それは綱渡りをしながら生きているボクの姿だ。

2014/12/05
Vol.243 黄色の雨

今年の黄葉は特別なのだろうか?
晴れた朝にも
曇天の北風が吹く午後にも、
黄色の葉が舞っている。
「ほらあ、ふってるよ」
路地裏や公園の片すみ、
いたるところで
子どもたちの歓声が聞える。
両手をあげて、葉を受け止めようと駆けだしていく。
生垣にもたれ日向ぼっこをする白髪の人は、
目を閉じたまま、まぶたの裏をかすめていく黄色の光を眺めている。
どこにもほほえみがある。
雨の日、地面は黄色の水たまりが出来たように輝いている。
深夜、駅前に設置された大きなクリスマスツリーにも黄色の葉は降り続く。
それがもう一週間も続いている。
ボクは落ち着かない。
落ち着かないのはボクだけではない。
彼らもそうだ。
路地裏の廃屋には、大きなイチョウの木があって、
いつもは街の中の影のような一画が妙に明るい。
閉ざされた門扉をくぐり、傾きかかった家の裏に回ると、
小さな池があるのだけれど、その水面にも黄色の葉はびっしり。
腐った縁側に座って、その輝きを見ていると、
いつのまにか辻堂の師匠(ネコ)が横にいるではないか。
みれば、世捨て犬や青い石をもつカエル、百年貝も池を囲むように黄葉に埋もれている。
「今年の黄葉は格別ですね。」
「うん、うん」
師匠は降り続く黄色の雨の感触を楽しむように目を閉じたままうなづく。
「この黄色はスーパーのレモンとかミカンの色とは違いますね。光が浸みこんでいるせいでしょうか?」
つまらないことを訊くなと、師匠は耳を掻きながら横を向く。
相手にされないので、ボクはポケットから最近知り合った仲間の絵を取り出して眺める。
すると師匠は、首を伸ばしてそれを覗き込む。
そこには牛やゾウやシマウマやねこの母子が描かれていて、おっぱいを飲んでいる。
もちろん人間の絵も描かれていて、人間の母子も他の動物と同じように裸なのだ。
師匠はその絵をながめ、短い手を伸ばし、何やらむにゃむにゃ呟き、また目を閉じる。
ボクは師匠に、動物も人間も対等に裸な絵の面白さを伝えたかったのだけれど、またバカにされそうなのでやめる。
廃屋の午後にも、黄色の雨は降り続き、心そこにあらずの時間が過ぎていく。

△ページトップへ戻る
2014/12/02
Vol.242 羊をかく時間

来年の干支を描く時期になってきた。
いくつかのフェースの場所を回りながら、仲間たちに干支を描いてもらっている。
来年は羊。
羊は仲間たちにとっては写真がなければイメージが浮かびづらい動物だ。
携帯や動物図鑑などをみながら、黙々と描いていく。
拒否する仲間は少ない。
1時間少し。
紙の上に薄灰の影を落とし、
パステルや色エンピツの走る音が聞こえる。
やわらかな線
ひろがっていくやわらかな色
仲間たちの間を回りながら、
それらをみていると、不思議な牧場に迷い込んだような気になる。
そこにあるのは、羊の形ではなく、絡み合うように湧き出してくる色だ。
色たちは集まり、大きな雲のように斜面を登り、
そのまま空に登っていく。
際限のない広大な牧場のあちこちで、
仲間たちは手慣れた牧童のように、色をつぎつぎと紡ぎ出している。
大きな安らぎとぬくもりが、世界を包んでいる。
生命?
ボクらを包む大きな生命?
仲間の紡ぎだす
先端の色をつまみあげ、
くるくる巻いていくと、
最後には生命の素肌が現われるのだろうか?
牧場全体がそんな風に大きな毛糸玉でできていて、
ボクらも
毛糸玉の一端にすぎないのかもしれない。
そんなことを考えながら、ぼーとしていると、
「これどう?」
小さな仲間が、ボクの肘をつつく。
カラフルな水玉模様、
スフインクスのような羊がこちらを見ている。

△ページトップへ戻る
2014/11/28
Vol.241 雨の朝

目覚めると、雨が降っていた。
震えながら悪夢から立ち上がり、窓越しに腕を差し出した。
腕に水の感触。
「ナルヨウニシカナラナイサ」
そんな言葉が口をつく。
その意味が自分にもよく分からない。
それでも、その言葉に癒やされようとする自分が背中に張り付いているのが分かる。
嫌な夢だった。
ほとんど消えかかっている夢の暗がりに虫のようなものがこそこそ隠れようとしている。
虫はいろいろなところにいて、スリッパのようなもので叩き潰そうとするのだが動きが速くすぐに姿を隠すのだ。
時々、叩くことに成功するのだが、潰れた体の一部を残して、本体は逃げてしまう。
潰れたところから黒い体液が流れ、悪臭がひどい。
オレは何をしてるのだろう?
夢の中で疲労困憊している。
雨は二の腕辺りまで垂れて、爪先を濡らしている。
「ソノママデイイジャンカ!!」
突然、硬い声が聞える。
「オマエ、ナニ考エテンノ?」「Kafkaノツモリカ?」
「ソウダ、ソウダ!」
ドングリのような声がころころ聞えてくる。
みると、たくさんの蟻が床を行進している。
TARO画伯の「アリさん、ゾロゾロ」から抜け出してきた蟻たちだ。
「ッタク、ナマイキナンダヨ!」
「ソウダ、ソウダ、ナマイキナンダヨ!!」
息巻いている。
「ソノママ、何モ考エズニ行ケ!」
「イケ!イケ!」
「ソウダ、ソウダ」
ワタシの足を蹴りあげている奴までいる。
一匹つまみ上げようと、腰を曲げると、あわてて逃げていく。
不意に雨の匂いが肺に広がる。
湿った落ち葉の匂い。
悪夢は去った。

△ページトップへ戻る

