このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。
「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、
「もちろん!」と嬉しいお言葉。
ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。
2016/08/12
Vol.365 「夏の花」

統合失調症で車椅子を使っているYさんからメールで夏の花が送られてきた。
指で描いたという、カンナのような真っ赤な花。
濃緑の葉が上方に向かって伸びている。
葉の周りを青い光が跳ねている。
ああ生きてるなあとボクは画像の前で静止する。
そのまま、放心する。
すると、赤い小魚の群れを緑色の魚たちが追い込んでいるような、
生死のドラマが見えてくる。
右往左往する赤い混乱、
ゆっくり追い詰めていく、しなやかでしたたかな緑の指跡。
二つの動きがボクの中で波紋のように広がっていく。
外はけだるい夏の暑さだけれど、
そこには根源のエネルギーが流れている。
Yさんは花だという。
もしかしたら、
花というのは幾つものエネルギーの流れ合っている現象なのかもしれないと思う。
花の色や形や時間は、絶え間のない生命の変化をボクらに伝えているのかもしれないと思う。
ああ生きてるなあ。
花辞典で見るカンナよりも、
花屋の店先で見るカンナよりも、
Yさんの花は生きてるなあと思う。
一週間後、
またYさんから画像が送られてきた。
こんどは「原爆」の絵だという。
前日が広島に原爆が投下された日だったので、そのニュースを見ながら描いたのかもしれない。
黒く縁どられた波模様の下に赤や黄色、緑、紫が花びらのように広がっている。
ボクは昨年、被爆70周年ピースアートイベントで広島市立特別支援学校高等部の生徒たちと描いた「ゲルニカ/HIROSHIMA」の6mの壁画を思い出す。
71年前のあの夏もこんな鮮やかな色が広島の街には咲き乱れていたに違いない。
そこに落ちてきた人類が作った巨大な光
その中心にある闇をYさんは黒い花びらのように描いたのかもしれない。
「原爆」も一つの花なのだろうかとボクは思う。
花だとしたら悲しい「夏の花」だ。
炎天下、
ボクは身を焼くように川沿いの道を歩いた。

2016/08/05
Vol.364 「目をそらしてはいけない」
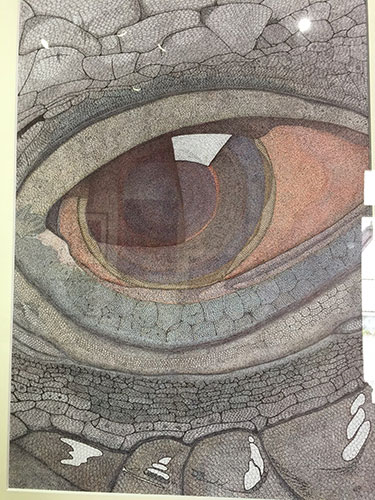
津久井やまゆり園の障がい者殺傷事件はとても考えることが多い。
新聞報道からうかがえる実行犯の言葉の闇は深い。
「同級生に障害者、不幸だと思った」
「家族と離れ、職員と意思疎通ができない障害者は生きていても仕方がない」
「障害者なんていなくなればいいと思った」
「事件を起こしたのは、不幸を減らすため」(朝日新聞2016.7.30)
多くのメディアは、実行犯個人の異常性を取り上げているが、こうした言葉の背景にあるのは弱者が強者によって抹殺されていく優生思想の存在だし、世界中に拡散しているヘイトクライムやジハードによる無差別殺人の正当化といった暗澹たる時代の感情なのは容易に想像がつく。
「識者」や「専門家」や「メディア」が、そこまで視野に入れた事件の分析、解明を行わなければ、殺された19人の人々は救われないなと思う。
でもボクはどうしても、支援員として仲間たちと一緒に生活していていた実行犯はどんな風景を見ていたのだろうということに想いが行ってしまう。
津久井の人里離れた施設で暗い観念に苦しむ実行犯に、仲間たちの笑顔や一心に何かを伝えようとする声や手足の動きは届かなかったのだろうか?
仲間たちと一緒に生活し、一緒に老いていく、そんな自分の生に喜びを見出すことはできなかったのだろうか?
それらは、いまのボクにはかけがえのない大切なものなので切なくなってしまう。
支援員の仕事は労働じゃないんだ、生き方なんだと思う。(だからといって、労働条件や賃金を無視していいなんては思っていないよ)
そこで生きる人は「お客様」や「利用者」じゃなくて、一緒に生きる「仲間」なんだと思う。
彼(実行犯)は、仲間の存在、生きてる日々を「不幸」と決めつけることで、山中の施設を隔離収容施設のように見ていたのかもしれない。
仲間たちを収容者として、一方的に管理する看守のような目をしていたのかもしれない。
それはきっと彼の「不幸」だったのだろうと思う。
仲間たちを隔離、管理することで自らの「不幸」という傷口をくりかえし傷つけていた孤独な日々が見えるような気がする。
彼の「不幸」の原点はどこにあったのだろう?
少なくとも「障害のある同級生を不幸」と思ってしまった少年期にあることは推測される。
一人ひとりの個性を啄んでしまうような過酷な中学生時代にしか出会うことができなかった障害のある同級生。そんな彼に仲間として向き合う時間や体験も許されず、ただ「不幸な存在」として一面的な観念を強いられ、受験競争の流れに身を置いていった少年。
人間的な感情や体験を奪われ、社会から清潔で安全というレッテルのついた籠(ボックス、セル)を与えられ、そこに閉じこもり、孤独な生、不幸をまとっていく少年。
実行犯の少年の姿がそんな風に浮かび上がってくる。
でも、その少年は、実行犯だけじゃない。
これを読んでるあなたやボクもきっと同じ姿をしているのだ。
少年期に「障害を不幸」と思わせる、目に見えない差別や悲しみの網のようなものがボクらの周りに繁茂しているのかもしれない。
どこ?
ほら、薄っぺらな笑いと暴力があふれるテレビの画面、
うつむいたままゲーム機に熱中する人たちが行き過ぎる街角、
静かに開かれる朝の学校のドア、
ため息をついて坂道を下っていく少年の影ぼうし、
ああ、ボクらの生きているいたるところに・・・

2016/07/29
Vol.363 「小宇宙フェースofワンダーの住人たち」

夏になった。
ボクは相変わらず仲間たちの間を往ったり来たりしている。
まるで昔、Hさんと作った絵本「海辺の一日」に出てくる「世捨て犬」みたいに、舌を垂らし、ハアハア切らし、暑い陽ざしの下を走っている。
何を急いでいるのか分からないけれど、とにかく仲間たちのいるところへ走っていって、おしゃべりし、また次の仲間たちのところへ走っていく。
おしゃべりするのは仲間達や一緒に来ているお母さんやお父さん、ガイドヘルパーの人たちだけとは限らない。
フェースのおしゃべりは楽しい。
手の動きや色彩や描線が言葉になる。
部屋を漂う視線や立ったり座ったり、いらいら机を叩く音も言葉になる。
もちろん叫びやジャンプも・・・
描かれた絵もいろいろな言葉をしゃべる。
T.T君の描いた三本指のカエルくんの絵にはいろんな言葉が行きかってる。
水の中を自由自在に泳ぎながら、どじょうやザリガニやたこやクジラたち、
オレンジやきみどり、あおむらさきの泡を吐きだしながら、しきりとしゃべっている。
彼らの話しに入り込むのはなかなか難しいけれど、ボクは距離を置いて耳を澄ます。
すると、とてもやわらかで、きいたこともない不思議な泡(あぶく)の声が聞こえてくる。
ボクらの言葉には翻訳不可能だけれど、ボクはとてもやさしい世界に包まれていくのを感じる。

次はK.H君の描いた莢(さや)に入ったカラフルな豆
この絵はボクに、この夏最高の勇気をくれた。
K君はこの二年ほど、心身ともに絶不調で、言葉がどんどん遠くに行ってしまい、歩き方も水中を歩いているようにゆっくりゆっくり・・・「おーい」と呼びかけるボクの声も届かないところを旅していたのだ。
そんな彼が再び、フェースの仲間のところに帰って来てくれた。
色彩豊かな言葉を話し始めたのだ。
ボクはフェースをやってよかったとあらためて思う。
それから、ミントアイスをほおばっているシロクマ君。
この絵はK.T君に頼んで描いてもらったエコ紙芝居の1シーン。
「おいおい、冷蔵庫あけっぱなしだぜ」と声をかけても知らんぷり。
相変わらずの自己チューキャラクター。
それにしてもしぶい禅風の味わいがあるね。
フェースの世界は奇妙な住人たちが往ったり来たり、
いろいろな言葉も浮いたり沈んだり、
会話もかみ合ったりかみ合わなかったり・・・
ボクもしっかりそんな小宇宙の住人なのだ。

2016/07/22
Vol.362 「ニキフォルはニキフォルである」

7月の暑い午後、千駄木の谷根千「記憶の蔵」で「ガード下学会」のみなさんと合同で「ニキフォル」の映画鑑賞会と茶話会を持った。
映画は、4万点を超える絵を煙草の裏紙や厚紙、チョコレートの包み紙などに描き、それを街頭で売ることで生計を立てたポーランドの異端の画家ニキフォルの誇り高い生涯を描いている。
各地の街並みを巡っている「ガード下学会」の人たちが、そんなニキフォルの風景をどのように見るのだろうというのが、今回の映画会のひそかな楽しみだった。
地下鉄から路上に出ると夏の暑い風が吹き抜けていた。
千駄木に降りるのは久しぶりだ。この界隈は昭和の下町の家屋を残してカフェやギャラリー、宿屋に改築した店舗が点在し、古いものと新しいものがうまくブレンドされた独特な雰囲気を持っている。
通りの風にもゆるい優しさがある。多くの人たちがゆっくり遊歩している。東京芸大が近いせいもあり、若者たちの姿も目立つ。
会場の「記憶の蔵」は団子坂を登ったところ、小さな児童遊園の木立ちの奥にひっそりとたっていた。
人一人がどうにか通れる狭い道を抜けると小さな入り口があり、一歩足を踏み入れるとすぐに蔵の暗がりに囲まれる。関東大震災にも生き残ったという建物は一見、廃屋というイメージだが、そこには人が生きてきた記憶を残そうとする強い意志のようなものがいきわたっていて、気持ちよく呼吸ができる。
集まってきたのは17名。
灯りが消され、すぐに上映が始まった。
腰が痛かったボクは椅子には座らず、床に横になって映像を見た。
何度も見ている映画だが、ニキフォルの言葉がボクの中に蓄積してくる。
「(美大を出たプロの画家である)お前さんの絵は下手クソダ」
「(建物は)下から描いていかなくては崩レチマウゾ」
「(美術館やコレクターには)絵はウラナイ」
「(美術館にある絵なんか)クダラナイ」
「(わしの絵は)香水、二本となら交換スル」
「(なんと言われようとベッドのある)ここから出テイクモンカ!」
「(きれいな服なんか)役にも立タナイ」
「(新しい服じゃ)恵ンデモラエナイ」
したたかで、傲慢な言葉が降ってくる。
それらはとてもクリアで美しい。
ボクはカエルの画家が、人物像を描くとき、服のすそから描いていたのを思い出す。
ボクの絵を見て仲間たちが「(先生の絵は)ツマラナイ」といった美術の時間を思い出す。
そうなんだよなあ、
ニキフォルはニキフォル、
君たちは君たちなんだよなあ。
いつか君たちも街頭で君たちの絵を売る日が来るのだろうか?
床に寝そべったボクの隣で、脳性麻痺の少年が時々足を延ばしてボクにちょっかいを出すのを楽しみながら、いい映画だなあとあらためて思った。

2016/07/15
Vol.361 「ずんずん、進んでいく」

長い間、仲間たちの絵に付き合っていると、そこで(描くのを)ストップしたらいいのにと思っているうちに、あっという間に線や色が描きなぐられ、表情が一変してしまうということがよくある。
仲間たちの絵はとどまることを知らない。
どこかで声をかけないとずんずん遠くへ行ってしまう。
小学2年生から一緒に絵を描いているRさん、
とても暑い朝、ミロコマチコの画集を見ていて、鳥を描き始めた。
「トリ、トリ・・・」
画集の赤い七面鳥をゆびさして、声にしながら、
一気にクレパスで四角い身体を描いた。
それから小さな頭。
それから「アシ、アシ、アシ・・・」
木の棒のような太い脚。
Rさんはいま中学2年生で、ついこの前までは頭に浮かんでくる文字や海や虹を描いていた。いまは自分の気に入ったものを見つけて、それを描き写すことに熱中している。
もちろんシンプルで、おおらかな色や線。
ボクはもうそれだけで十分だと思う。

次は色を塗る。
パレットに緑、
それから赤、青・・・
まるで料理をするみたいに迷いなく、筆を立てて混ぜていく。
あざやかな緑と赤が土の色に変わっていく。
それをクレパスの鳥に塗っていく。
柔らかな命のような色がパッチワークされていく。
力強い筆の跡。
それはRさんの腕からほとばしり出た命の跡だ。
ああ、いいなあとボクは思う。
もうそれで十分だと思う。
でも、彼女は描くことをやめない。
ずん、ずん、ずん、進んでいく。
「シロ、シロ、シロ・・・」
Rさんはまるで刺し子のように、パッチワークの身体に白い点々をつけていく。
鳥の身体に雨が降っている。
風が吹いている。
草がずんずん伸び始める。


